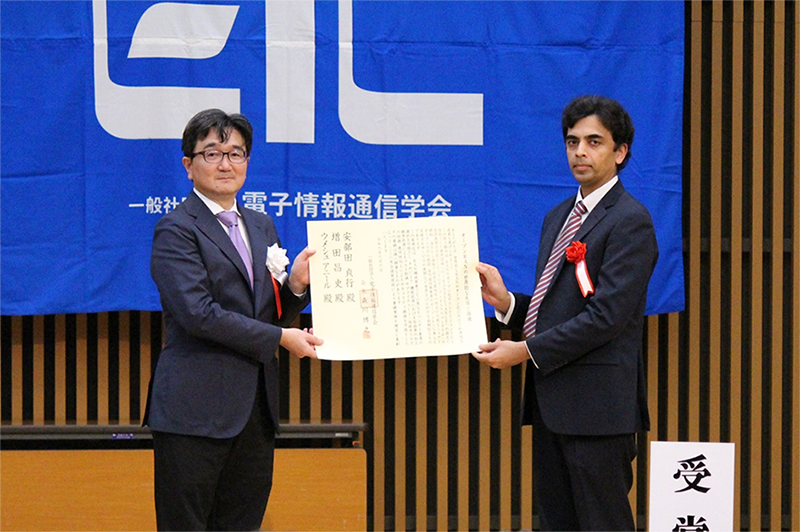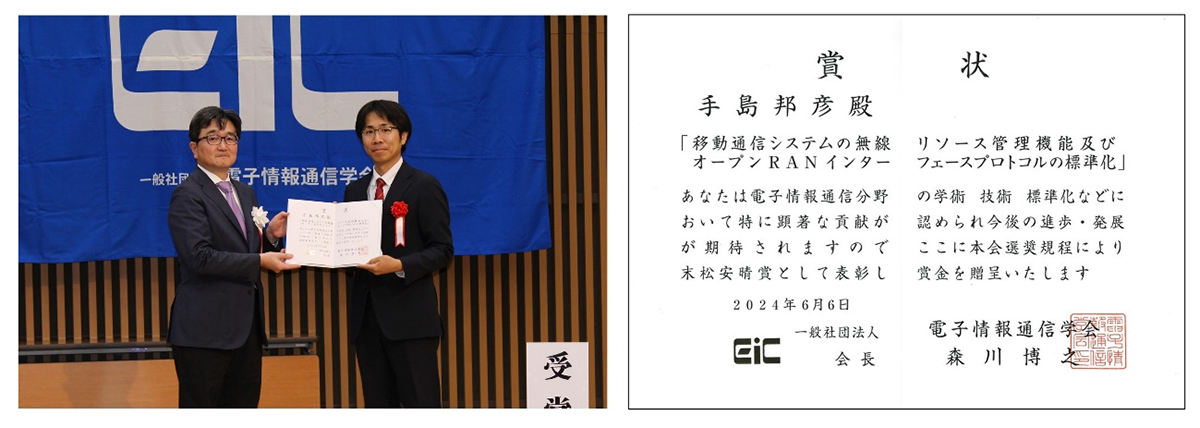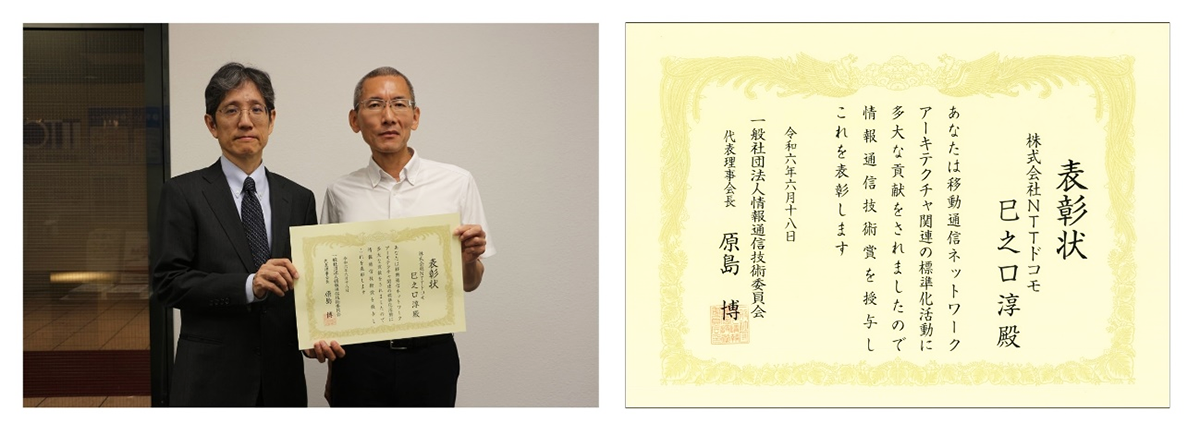電子情報通信学会2023年度「通信ソサイエティ論文賞」受賞
2024年5月17日に一般社団法人電子情報通信学会通信ソサイエティより,ドコモ北京研究所の劉 娟,侯 暁林,劉 文佳,陳 嵐と6G-IOWN推進部の岸山 祥久†1,浅井 孝浩†2が,共著英文論文「Unified 6G Waveform Design Based on DFT-s-OFDM Enhancements」に対する2023年度通信ソサイエティ論文賞のBest Paper Awardを受賞しました.本賞は,2022年10月から2023年9月までの1年間に電子情報通信学会通信ソサイエティの英文論文誌に掲載された論文の中で特に優秀と認められた論文に与えられるものです.
波形設計は重要な6G研究課題の1つです.受賞の対象となった論文は,異なる6G波形スキームの候補技術と長短所に対する全面的な分析に基づいて,6G波形のスペクトル効率,電力効率と帯域外漏洩性能が向上できる6G統一波形設計スキームを提案しています.具体的には4G/5G波形DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)*1をコアとし,DFTモジュールの前後信号処理によって波形整形(圧縮と拡張)を実現し,波形性能を向上させます.論文はリンクレベルシミュレーションに基づいて,提案スキームと従来の6G候補波形スキームに対してコンピュータシミュレーションによる性能比較を行い,提案スキームの性能ゲイン(例えば,ミリ波のカバレッジの1kmから1.5kmへの拡大など)を検証しました.
本論文の研究課題(6G波形)は重要性と先駆性を有すること,提案技術は創造性と新規性を有した上,コンピュータシミュレーションを通じて提案スキームの有効性を検証したことが評価され,今回の論文賞受賞に至りました.ドコモ北京研究所は,2025年に始まる6G標準化に向けて,6Gの先行研究における技術革新を推進していきます.
- †1 現在,6Gテック部(株式会社Space Compassへ出向中)
- †2 現在,クロステック開発部
- DFT-s-OFDM:OFDM送信において,IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)の前段にDFTを設けることによりシングルキャリア伝送を実現する方法.4G/5Gにおいて上りリンク伝送法として採用されている.
2023年度電子情報通信学会「業績賞」受賞
2024年6月6日に一般社団法人電子情報通信学会より,無線アクセスデザイン部の増田 昌史,OREX SAIの安部田 貞行,ウメシュ アニールは,「オープンRANの世界的な先導と推進」の功績により2023年度電子情報通信学会業績賞(ロ)号を受賞しました.
業績賞(ロ)号は,電子工学および情報通信に関する新しい機器,または方式の開発,改良,国際標準化で,その効果が顕著であり,近年その業績が明確になったものに対して贈られるものです.
受賞者らは,世界の携帯電話事業者と連携し2018年2月にRAN(Radio Access Network)のオープン化やインテリジェント化を目的とした業界団体「O-RAN ALLIANCE」(O-RAN)を設立し,標準化をリードしてきました.また,2021年2月にはオープンRANの世界展開を目的とした「5GオープンRANエコシステム」をグローバルベンダとともに開始し,2022年2月には海外から遠隔で仮想化基地局の検証が可能なシェアドオープンラボを開設,2022年10月に英Vodafone Group PlcとオープンRAN推進の協業に向けた協力に合意,2023年9月にはTCO(Total Cost of Ownership)を最大30%削減,消費電力を最大50%削減可能にする「OREX(Open RAN Ecosystem Experience)®」サービスラインナップを発表し,海外通信事業者のオープンRAN導入支援体制を強化するなど,RANオープン化を世界でリードしています.
さらに,受賞者らは,O-RAN仕様を用いてマルチベンダで構成した5G基地局装置の相互接続を世界で初めて成功させ,ドコモは2019年9月よりO-RAN ALLIANCEの装置間インタフェース仕様を用いて5Gプレサービスを開始しました.2020年3月には5G商用サービスを開始し,2020年9月にはマルチベンダRANでの5G周波数キャリアアグリゲーションの商用化を世界に先駆けて実現させました.さらに,2022年8月には送受信とも最大値が1Gbpsを超える5G SA商用サービスを開始,2023年9月に仮想化基地局(vRAN(virtualized RAN))およびインテリジェント化(RIC(RAN Intelligent Controller))の商用運用を開始するなど,O-RAN仕様の普及・拡大を牽引しています.
このようなRANオープン化の拡大により,RAN構成要素ごとに複数ベンダから選択が可能となります.これにより,機能拡張における自由度が向上し,競争促進によるコスト削減,サプライチェーン・地政学リスクの回避が実現できます.また,透明性向上によるセキュリティ確保も可能となります.
2023年度電子情報通信学会「末松安晴賞」受賞
2024年6月6日に一般社団法人電子情報通信学会より,無線アクセスデザイン部の手島 邦彦は,「移動通信システムの無線リソース管理機能及びオープンRANインターフェースプロトコルの標準化」の功績により末松安晴賞を受賞しました.
末松安晴賞は,電子情報通信分野において,学術,技術,標準化などにおいて特に顕著な貢献が認められ,今後の進歩・発展が期待される若手研究者・技術者・実務家に授与されるものです.
手島は,3GPP(3rd Generation Partnership Project)の標準仕様策定のため数多くの技術提案を行うとともに,標準必須特許の発明も行ってきました.特に,異なる基地局間の周波数を束ねて利用する技術(デュアルコネクティビティ)による,LTE-Advancedや5Gネットワークにおける高トラフィックエリアでの基地局高密度化の促進や移動端末の高性能化に寄与してきました.また,3GPPの作業部会では,世界各国の通信事業者やグローバルベンダの参加者を代表して取りまとめ役(ラポータ)にも指名され,リーダシップを発揮し,新幹線のように高速移動環境下での移動端末の送受信性能の改善に寄与する標準仕様の策定を実現しました.
さらに,O-RAN ALLIANCEにおいても作業部会の共同議長やスペックエディタを務め,異なるベンダが提供するCU(Central Unit)装置とDU(Distributed Unit)装置や,DU装置とRU(Radio Unit)装置を相互接続可能とする技術仕様の策定に加え,当該仕様に準拠した装置であることを確認するテスト規定や,当該装置間の相互接続性を保証するテスト規定の策定も牽引してきました.これらの活動を通じ,よりオープンでインテリジェントな無線アクセスネットワークの産業界への早期普及に大きく寄与しました.
手島の功績は,携帯電話システムの発展・実用化に欠かせないものばかりであり,今回の受賞は,産業界への貢献が極めて大きいことが評価されたものです.
情報通信技術委員会(TTC)2024年度「TTC会長表彰」受賞
2024年6月18日に一般社団法人情報通信技術委員会(TTC:The Telecommunication Technology Committee)より,2024年度情報通信技術賞の受賞者が発表され,6Gテック部の巳之口 淳が「移動通信ネットワークアーキテクチャ関連の標準化活動にかかわる功績」によりTTC会長表彰を受賞しました.
TTCは,情報通信ネットワークにかかわる「標準」を作成することにより,情報通信分野における標準化に貢献するとともに,その普及を図ることを目的とした組織であり,その目的に沿う事業の遂行に多大な貢献をした者に対して毎年表彰が行われています.
巳之口は,移動通信コアネットワークのサービス要求条件・アーキテクチャの専門家としてITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector),3GPP(3rd Generation Partnership Project)における標準化活動,オペレータ団体での国際協調を実施してきました.2001年から2008年までITU-T SSG(Special Study Group),SG(Study Group)19(Mobile Telecommunications Networks)に参画し,TTC 4G検討の成果を持ち込み,Systems Beyond IMT-2000勧告群の作成に寄与しました.2006年から2011年までNGMN(Next Generation Mobile Networks)に参画し,LTE/SAE(System Architecture Evolution)商用化推進とともに,4G移行期音声通信のCSFB(Circuit Switched FallBack)への統一化議論を主導しました.
2011年以降は継続して3GPPに参画し,第4世代移動通信システム(4G)ではアクセス規制関連項目のラポータを務めSSAC(Service Specific Access Control) connectedモード対応を仕様化,第5世代移動通信システム(5G)では,4Gと5Gの両方を使ったEN-DC(E-UTRA NR Dual Connectivity),NSA(Non-Stand Alone)の早期仕様完成や,統一アクセス規制(UAC:Unified Access Control),ネットワークスライスの仕様化に貢献しました.長年にわたるこれらの貢献が認められ,今回の受賞となりました.
「2024 Japan AWS Top Engineers」「2024 Japan AWS Jr. Champions」受賞
2024年6月20~21日に幕張メッセで開催されたAWS Summit Japan 2024において,サービスイノベーション部の中村 拓哉が「2024 Japan AWS Top Engineers (Security)[1]」を,サービスイノベーション部の小澤 遼,保延 渉が「2024 Japan AWS Jr. Champions[2]」を受賞しました.ドコモとして,「2024 Japan AWS Jr. Champions」は初の受賞となります.
なお,中村と小澤はAWS認定資格をすべて保持しているAWSエンジニアに贈られる「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」も同時に認定されました.
今回の表彰は,APN(AWS Partner Network)参加企業に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムで,「2024 Japan AWS Top Engineers」とは,特定のAWS認定資格をもち,AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている方,または技術力を発揮したその他の重要な活動や成果がある方を表彰するもので,AWS Japanがそれらを審査し選出します.また,「2024 Japan AWS Jr. Champions」は応募時点で,社会人歴1~3年目の突出したAWS活動実績がある若手エンジニアを表彰するもので,AWSを積極的に学び,自らアクションを起こし,周囲に影響を与えているAPN若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する表彰プログラムです.
中村は,ドコモグループにおいてパブリッククラウド活用を推進するチームであるCCoE(Cloud Center of Excellence)の技術リードとして,社内勉強会の開催や「2024 Japan AWS Jr. Champions」の選出に向けた若手エンジニアの育成,クラウドセキュリティ高度化のための統制基盤の提供,社内外での幅広い案件対応などといった活動が高度な技術力を発揮していると評価され,「2024 Japan AWS Top Engineers」受賞となりました.
小澤は,5GSA(Stand Alone)基地局 - 携帯電話端末間のデータを分析する基盤システムの最難関機能の開発の主導,年間数億円規模の社内のAWSコストの削減に貢献したことや,その取組みを登録者3,000名にも及ぶ大規模なイベントで発表したことが評価され,「2024 Japan AWS Jr. Champions」受賞となりました.
保延は,AWSサービス「Amazon Bedrock」を利用している社内チームからの要望を,「AWS re:Invent 2023」中に行われたEBC(Executive Briefing Center)にてAWSに直接伝えたことや,社内勉強会・報告会における活動,日経クロステックActiveでAWS活用に関する記事[3][4]を執筆したことが評価され「2024 Japan AWS Jr. Champions」受賞となりました.
文献
- [1] AWS:“2024 Japan AWS Top Engineers の発表.”
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2024-japan-aws-top-engineers/
- [2] AWS:“2024 Japan AWS Jr. Champions の発表.”
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2024-japan-aws-jr-champions/
- [3] 保延 渉:“社内情報が漏洩,AWS検証環境でコンテンツが一般公開される落とし穴とは,”日経クロステックActive,Jun. 2023.
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00467/060100004/
- [4] 保延 渉:“たった1週間で高額な費用に,AWSの機械学習サービスに潜む落とし穴,”日経クロステックActive,Mar. 2024.
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00467/030800013/
第35回電波功績賞「電波産業会会長表彰」受賞
2024年6月25日に開催された第35回電波功績賞表彰式において,NTN推進グループ(代表 田村 穂積)が,「2.5GHz/2.6GHz帯国内衛星移動通信システムの高度化に関する開発・実用化」の功績により電波産業会会長表彰を受賞しました.
電波功績賞は,一般社団法人電波産業会(ARIB:Association of Radio Industries and Business)により,電波の有効利用に関する調査,研究,開発において画期的かつ具体的な成果を上げた者,あるいは電波を有効利用した新しい電波利用システムの実用化に著しく貢献した者に対して授与されるものです.
受賞者らは,LTE方式の通信性能と超大型展開アンテナ搭載のデジタルハイスループット通信衛星N-STAR e号機の中継器性能を有効利用し,従来の6倍以上の同時接続数(音声換算:12,000以上),3GHz帯以下の衛星移動通信システムとして世界最速の下りデータ通信速度(最大3Mbps/従来の約8倍)を実現した衛星移動通信サービス「ワイドスターⅢ」を2023年10月より提供開始し,電波の有効利用に大きく貢献したことが評価され,今回の受賞となりました.
令和6年度全国発明表彰「発明賞」受賞
2024年7月11日に行われた令和6年度全国発明表彰式で,モバイルイノベーションテック部の寺田 雅之,マーケティングイノベーション部の小林 基成,ドコモ・テクノロジ サービスインテグレーション事業部の岡島 一郎が「携帯端末の基地局情報を用いた高精度でリアルタイムな人口推計の発明」により「発明賞」を受賞しました.
全国発明表彰は,大正8年,我が国における科学技術の向上と産業の発展に寄与することを目的に始まり,多大な功績をあげた発明,考案,または意匠,あるいは,その優秀性から今後大きな功績をあげられることが期待される発明などを表彰しています.科学技術的に秀でた進歩性を有し,かつ顕著な実施効果をあげている発明に対して,最も優秀と認められる発明に「恩賜発明賞」,特に優秀と認められる発明に「内閣総理大臣賞」「特許庁長官賞」などが贈呈されます.
受賞した発明は,携帯電話ネットワークの運用データに基づいて日本全国の人口分布の推移を推計する人口推計技術の中核となる,携帯端末の在圏数推計に関する基本発明です.
当該技術の実現にあたっては,基地局単位の在圏端末数を信頼できる形で推計する手段が必要不可欠ですが,そもそも携帯電話ネットワークはこのような応用が想定されておらず,在圏端末数を把握する手段がありません.そこで本発明では,ある時点における携帯端末の在圏状況を示す運用データに着目し,これを用いて在圏端末数を推計しています.ある期間における在圏端末数の平均は,その期間内における各端末の滞在時間の総和を期間長で除したものと等しい,という関係に基づいて在圏端末数を偏りなく高速に推計できます.
本発明は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策に広く役立ててもらうとともに,数時間先の渋滞を実用的な精度で予測するサービスの実用化に繋げるなど,さまざまな分野において社会・産業の課題解決や最適化への貢献を続けています.
「LAVAL Virtual Award」を受賞
2024年7月28日から8月1日までアメリカのデンバーにて開催されたアメリカコンピュータ学会(ACM:Association for Computing Machinery)SIGGRAPH 2024において,モバイルイノベーションテック部の石川 博規が,慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 南澤 孝太教授らとともに,Emerging Technologiesに採択され展示した「FEELTECH Wear: Enhancing Mixed Reality Experience With Wrist-to-Finger Haptic Attribution」により,「LAVAL Virtual Award」を受賞しました.
ACM SIGGRAPHは,Computer GraphicsとInteractive Techniqueにおける世界最高峰の国際会議で,Emerging Technologiesはグラフィックスとインタラクションの最先端の開発に焦点を当てた展示プログラムです.
今回の受賞は,これまでにないバーチャルとリアルを融合した触覚体験を高いクオリティで実現したことが評価されたものです.
LAVAL Virtual Awardを受賞したことで,2025年4月に行われる世界最大級のVR・ARの大会であるLaval Virtual 2025への出展が決定しました.
世界最高峰のデータ分析競技会「KDD CUP 2024」で入賞
2024年8月26日に,クロステック開発部の鈴木 明作,サービスイノベーション部の宮木 健一郎,前沖 翔によるチーム(チームA),サービスイノベーション部の橋本 雅人,R&D戦略部の落合 桂一,クロステック開発部の吉川 裕木子によるチーム(チームB)の計6名がデータ分析競技会であるKDD CUP 2024に参加し,チームAは2つのタスクで世界第6位,チームBは1つのタスクで世界第8位に入賞しました.
KDD CUPは国際計算機学会(ACM:Association for Computing Machinery)が主催するデータマイニング関連の国際会議KDD(Knowledge Discovery and Data Mining)で開かれるデータ分析競技会で,1997年,まだビッグデータやデータサイエンティストという言葉が無い時代から続く世界最高峰かつ最も歴史のあるデータ分析競技会です.
2024年の競技会は,①学術論文のグラフマイニング,②大規模言語モデルを用いたEコマースデータの解析,③ウェブ検索結果を活用した質問応答をテーマとした3つの部門で実施され,ドコモのチームは学術論文のグラフマイニング部門で入賞しました.当部門では,さらに3つのタスクが実施され,それぞれのタスクで以下のとおり入賞しました.
- 6位入賞 論文著者割当て:本タスクは,同姓同名の著者や,著者が異なる名前のバリエーションを使用するなどの名前の曖昧さにより,正しい著者に割り当てられていない論文を検出する精度を競うものです.チームAは,文章をベクトル化するBERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)というAIやword2vecといった手法を用いて,論文ごとの特徴や著者間の関係を数値化することでAIの検出精度を高めました.さらに,ツリーベースやニューラルネットワークベースなどの複数のAIを用いたアンサンブル学習により,高い検出精度を達成しました.
- 6位入賞 学術論文検索:本タスクは,与えられた専門的な質問の回答として最も関連性の高い論文を検索するモデルの精度を競うものです.チームAは,関連性のあるデータと無関係なデータのペアを学習するSimCSE(Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings)という手法と,質問に対する仮想的な回答を,大規模言語モデルを用いて生成するHyDE(Hypothetical Document Embeddings)という手法を組み合わせ,候補となる論文を絞り込むAIを開発しました.さらに,1段階目で候補論文を絞り込んだ後,2段階目で複数の分類モデルによってランキング化するという2段の構成により,効率的かつ高い精度で予測を行うことに成功しました.
- 8位入賞 引用論文追跡:本タスクは,与えられた論文が引用した複数の参考文献の中から,最も論文に影響を与えた参考文献を評価する精度を競うものです.チームBは,影響力の大きい引用論文はそのタイトルと引用元のテキストの類似性が高い点に注目し,文章をベクトル化するBERTを学術論文に特化させたSciBERTというAIを活用して,論文の文章と引用文献の類似性を評価しました.この手法では,まず1段階目でその類似性の評価を実施し,引用回数や共著者の数などの数値と合わせることで特徴量を作成しました.次に2段階目でその特徴量を用いた複数の分類モデルでアンサンブル学習を行い,これらの2段の構成により,より高い予測精度を達成しました.
ドコモは2016年からKDD CUPへの参加を続け,今回は2023年の入賞につづく,6回目の入賞となります.ドコモでは多数のデータサイエンティストを擁し,日頃からパートナー企業との共創の中で,AI・ビッグデータを有効活用し,さまざまな課題の解決に取り組んできたことが,今回の受賞に繋がりました.本大会で評価された世界最高レベルのAI・ビッグデータ分析技術を活用し,AI・ビッグデータ活用ビジネスの拡大とともに社会課題解決の取組みを促進していきます.