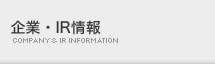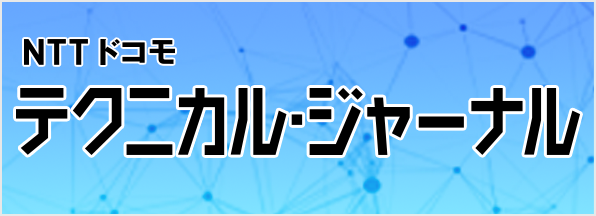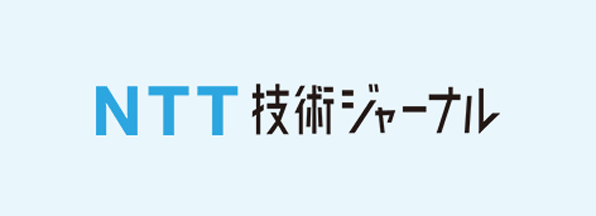容量/エリア拡大・国際ローミングを実現する携帯電話無線回路技術〜4.Super 3G標準搭載に向けた無線送受信回路技術の技術課題
Super 3Gは3GPP においてLTE(Long Term Evolution)と称して仕様策定作業が進められており、2007年12月に技術仕様書[15]がリリースされた。今後、商用に向けた開発が本格化するものと考えられる。本章では、Super 3G方式を実現するうえでの無線送受信回路の技術課題およびSuper 3G対応移動端末の商用化に向けた開発動向について述べる。
4.1 無線送受信回路への要求条件
Super3G移動端末の基本仕様を表3に示す。この表に示す方式要求に対して送信回路を実現する際の技術的な懸念点を次に示す。
| 表3 Super 3G移動端末の基本仕様 | |||
| 項目 | 仕様 | ||
| 使用する周波数帯 | W-CDMAと同じ(表1参照) | ||
| システム帯域幅 | 最大20MHz | ||
| 多重化方式 | FDD | ||
| 送信 | 無線アクセス方式 | SC-FDMA | |
| 変調方式 | QPSK, 16QAM | ||
| 送信出力 | +23dBm | ||
| 送信帯域幅 | RB(=180kHz)単位で可変 | ||
| 受信 | 無線アクセス方式 | OFDMA | |
| 変調方式 | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| 受信アンテナ数 | 2(1GHz以下は議論中) | ||
| 受信帯域幅 | システム帯域幅と同じ | ||
OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access
RB:Resource Block
- SC-FDMA[16]方式の採用および16値直交多値変調(16QAM:16 Quadrature Amplitude Modulation)
 1の適用により、非線形歪による劣化が顕著に現れる。
1の適用により、非線形歪による劣化が顕著に現れる。 - W-CDMAとの共存のために隣接チャネル漏洩電力が帯域幅に関係なく規定される。そのため、これまで以上に低く抑える必要がある。
- ピーク電力対平均電力比(PAR:Peak to Average Ratio)の高い信号への緩和策として、MPR(Maximum Power Reduction)という規定が設けられているが、エリア制限につながるため、運用上は適用しないことが望ましい。
またこれらに加え、移動端末には、発熱問題、連続使用時間への配慮も必要である。こうした理由から、Super 3Gの送信回路に対しては、高効率を維持しながらの線形性の向上を図っていくことが必要となる。このような課題に関して、これまでは電力増幅器(PA:Power Amplifier)の性能向上により達成してきたが、素子の限界に近づいており、今後は線形補償技術[17]の適用を検討していく必要がある。
次に、受信回路の技術課題を挙げる。
- 広帯域、高精度化
下り最大スループットを実現(64値直交多値変調(64QAM) 2、20MHz受信)するために、受信EVMの改善、受信帯域の拡張が必要となる。
2、20MHz受信)するために、受信EVMの改善、受信帯域の拡張が必要となる。 - 干渉波耐力の向上
既存システムとの共存のため、サービス帯域幅に関係なく、干渉波耐力を維持することが必要である。 - MIMO(Multiple Input Multiple Output)対応
1GHz以上の周波数帯(適用周波数は議論中)において、2系統の受信機の搭載が必須である。
これらの課題に対しては、ADCの高速・高精度化を実現したうえ、3章で述べたデジタルRF方式をベースに小型化および精度向上を図っていく必要がある。
 1 16値直交多値変調(16QAM):デジタル変調方式の1つで、振幅と位相の異なる16通りの組合せに対して、それぞれ1つの値を割り当てることにより、同時に4bitの情報を送信可能。
1 16値直交多値変調(16QAM):デジタル変調方式の1つで、振幅と位相の異なる16通りの組合せに対して、それぞれ1つの値を割り当てることにより、同時に4bitの情報を送信可能。 2 64値直交多値変調(64QAM):デジタル変調方式の1つで、振幅と位相の異なる64通りの組合せに対して、それぞれ1つの値を割り当てることにより、同時に6bitの情報を送信可能。
2 64値直交多値変調(64QAM):デジタル変調方式の1つで、振幅と位相の異なる64通りの組合せに対して、それぞれ1つの値を割り当てることにより、同時に6bitの情報を送信可能。
本記事は、テクニカル・ジャーナルVol.16 No.2に、掲載されています。