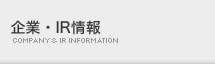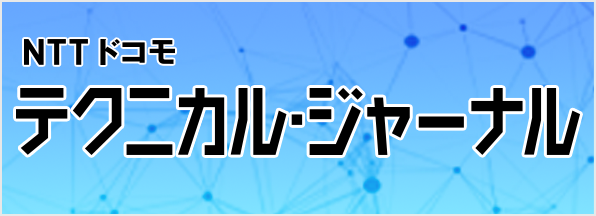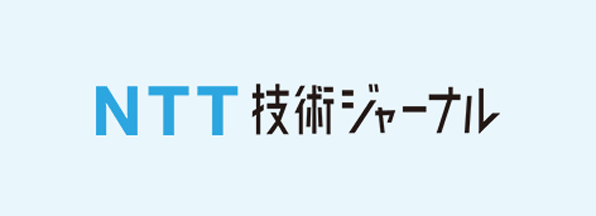携帯電話の快適な利用を目指した電池パック・充電器の開発〜3.電池パックの性能向上
リチウムイオン電池とは、内部の電極間でリチウムイオンを移動させて充電や放電を行う電池である。移動端末に使用した電池パックの歴史を図2に示す。1995年ごろにリチウムイオン電池が使われ始め、2008年現在までの約13年間でエネルギー密度が約2倍になっている。この進歩により、本移動端末の基本スペックである待受け時間も2倍以上になっている。
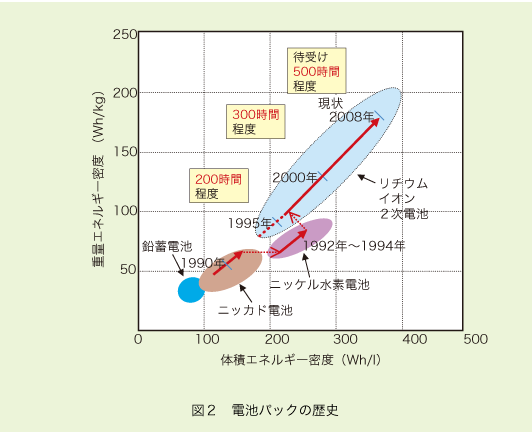
電池パックの内部構成を図3に、移動端末の電池パックを開発する際の3つの基本的な評価項目を以下に示す。
 電池パックの充電特性および保護回路動作
電池パックの充電特性および保護回路動作 電池パックの寿命評価、劣化診断
電池パックの寿命評価、劣化診断 電池パックの安全評価
電池パックの安全評価
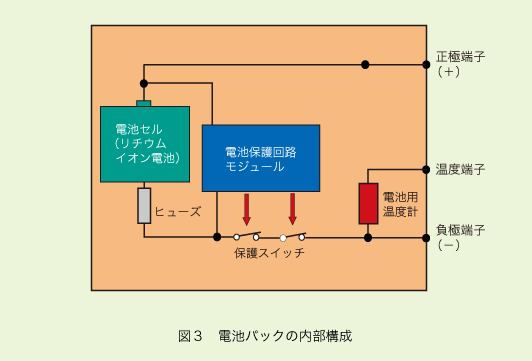
![]() 電池パックの充電特性および保護回路動作
電池パックの充電特性および保護回路動作
電池パックの充電特性を図4に示す。充電動作は2つの期間があり、微小電流を流して電池をチェックする予備充電期間と実際に充電電流を流す本充電期間がある。本充電期間では、電池電圧が4.2Vに達するまでは定電流を流し、4.2Vに達した時点で、電流を垂下させ、規定の電流まで減少した段階で満充電と判断する。一方、充電中に電池セルに過大な電圧や電流が印加された場合、故障や不安全な振る舞いが発生する恐れがある。これを防ぐために、図3に示す電池保護回路モジュール![]() 1が電池セルの状態を監視して各種保護を行っている。図5に同モジュールの保護動作条件を示しており、過充電や過放電が発生した場合に、充電停止などの保護が働く。
1が電池セルの状態を監視して各種保護を行っている。図5に同モジュールの保護動作条件を示しており、過充電や過放電が発生した場合に、充電停止などの保護が働く。
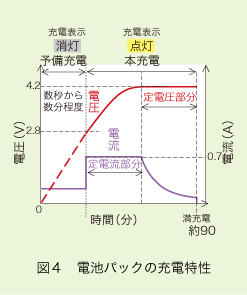
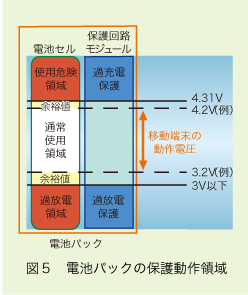
![]() 電池パックの寿命評価、劣化診断
電池パックの寿命評価、劣化診断
電池パックの寿命評価では、内部の電池セルの劣化や寿命特性の評価技術の確立が必要である。一般に、移動端末以外のモバイル機器用の電池は、完全充電と完全放電を繰り返すサイクル的な使用が主流である。この場合、電池の劣化モードの1つであるサイクル劣化![]() 2が発生する。しかし、移動端末は主として充電、通話、待受けの3つの状態があり、電池セルとしてはサイクル劣化のほかに、充電状態を長時間保持することによる劣化モードである、保存劣化
2が発生する。しかし、移動端末は主として充電、通話、待受けの3つの状態があり、電池セルとしてはサイクル劣化のほかに、充電状態を長時間保持することによる劣化モードである、保存劣化![]() 3も発生する。移動端末の3つの状態に対して電池の状態(経過時間)が変化したときに、電池セルの劣化特性を測定した。1年使用経過後の電池セルの寿命特性の測定例を図6に示す。横軸は1日の通話時間、縦軸は電池容量
3も発生する。移動端末の3つの状態に対して電池の状態(経過時間)が変化したときに、電池セルの劣化特性を測定した。1年使用経過後の電池セルの寿命特性の測定例を図6に示す。横軸は1日の通話時間、縦軸は電池容量![]() 4、図中のTsは充電間隔(0.5日、1日おきなど)を示している。図6から、電池容量が左下がりで低下していること、充電間隔が短いほど電池容量が低下していることが分かる。この結果から、通話することなく頻繁に充電を繰り返す動作は電池劣化を速め、さらに、電池の測定条件として通話30分、充電頻度1日とした場合、1年間に約2割電池容量が低下するので、一般的に電池容量が4割低下すると電池の寿命であることから、約2年で寿命(取替え)と分かる[2]。
4、図中のTsは充電間隔(0.5日、1日おきなど)を示している。図6から、電池容量が左下がりで低下していること、充電間隔が短いほど電池容量が低下していることが分かる。この結果から、通話することなく頻繁に充電を繰り返す動作は電池劣化を速め、さらに、電池の測定条件として通話30分、充電頻度1日とした場合、1年間に約2割電池容量が低下するので、一般的に電池容量が4割低下すると電池の寿命であることから、約2年で寿命(取替え)と分かる[2]。
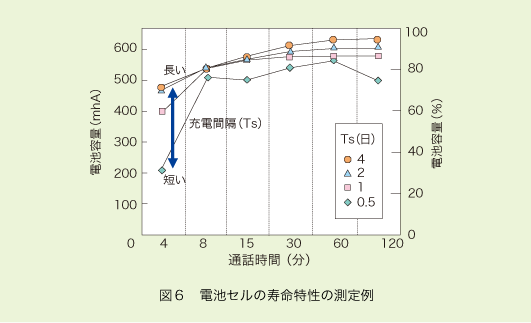
一方、移動端末の通話時間減少などの使用感に頼っていた電池交換を、自動的に電池パックの劣化診断することも重要である。電池セルの交流インピーダンス(1kHz時)の値と電池容量の劣化度合いの関係を測定した例を図7に示す。事前にこのデータが用意できれば、実際の測定対象の電池の内部インピーダンス値を計ることにより、瞬時に電池容量を推定することができ、電池取替え時期を的確に知らせることが可能となる[3]。
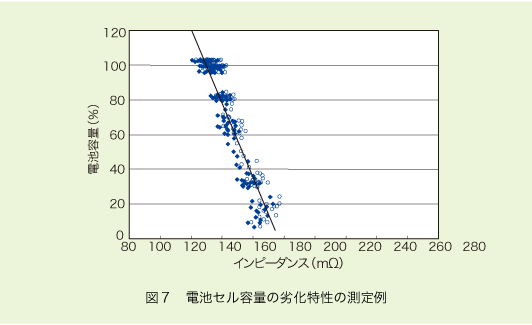
![]() 電池パックの安全評価
電池パックの安全評価に関しては、電池パックが落下や高温などの異常使用された場合でもある程度の安全性を確保されていることの確認試験を実施している。電池パックの異常使用の想定ケースを表2に示す。想定されるケースに即した試験条件を設定し、過電圧、圧壊試験および高温試験などを実施して安全な電池を確認し、商用の移動端末に使用している[4]。
電池パックの安全評価
電池パックの安全評価に関しては、電池パックが落下や高温などの異常使用された場合でもある程度の安全性を確保されていることの確認試験を実施している。電池パックの異常使用の想定ケースを表2に示す。想定されるケースに即した試験条件を設定し、過電圧、圧壊試験および高温試験などを実施して安全な電池を確認し、商用の移動端末に使用している[4]。
| 表2 電池パックの異常使用の想定ケース | |||
| 使用環境 | 原因 | 影響 | 確認試験 |
| 過充電 (高電圧、大電流) |
規格外充電 非純正充電器使用 |
膨れ、漏液、 発煙、発火など |
過電圧 印加試験 |
| 電池端子短絡 | 電池パック単体での チェーンショートなど |
温度上昇、 漏液、発火 |
短絡試験 |
| 電池破損 | 落下、圧壊の影響 | 温度上昇、 漏液など |
複合試験 (圧壊+劣化試験) |
| 水濡れ | 不用意な水中投下 | 膨れ、充電不可 (端子腐食) |
塩水水没試験 |
| 高温放置 | 炎天下の車中など | 容量劣化、 膨れ、漏液 |
高温試験 |
 1 電池保護回路モジュール:移動端末の電池パックの中にあり、リチウムイオン電池を外部からの過電圧や過電流から保護を行う回路。
1 電池保護回路モジュール:移動端末の電池パックの中にあり、リチウムイオン電池を外部からの過電圧や過電流から保護を行う回路。 2 サイクル劣化:電池の電池容量の低下原因の1つ。電池の充電と放電を繰り返すことによって発生する電池の劣化現象のこと。
2 サイクル劣化:電池の電池容量の低下原因の1つ。電池の充電と放電を繰り返すことによって発生する電池の劣化現象のこと。 3 保存劣化:電池の電池容量の低下原因の1つ。充電状態の電池を長期間維持(保存)することによって発生する電池の劣化現象のこと。
3 保存劣化:電池の電池容量の低下原因の1つ。充電状態の電池を長期間維持(保存)することによって発生する電池の劣化現象のこと。 4 電池容量:電池パックの実際の放電可能な電気容量の総量。電池パックを放電させて放電電流と放電時間の積により算出。
4 電池容量:電池パックの実際の放電可能な電気容量の総量。電池パックを放電させて放電電流と放電時間の積により算出。
本記事は、テクニカル・ジャーナルVol.16 No.2に、掲載されています。